全アイディアが事業化に向けて前進。JR博多シティの新規事業プロジェクトが得た確かな手応え
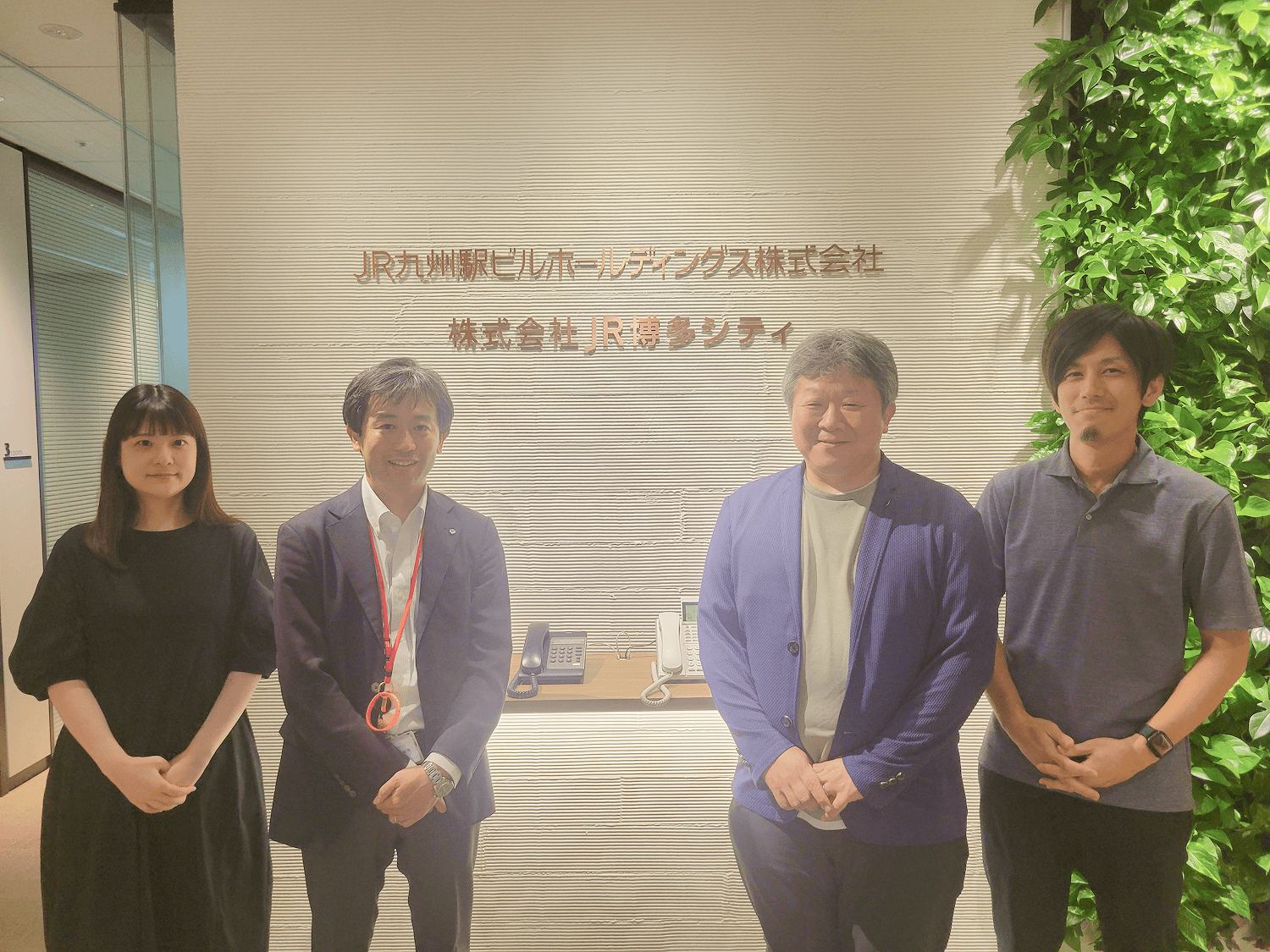
新規事業メンタリング事例
- 公募型の新規事業プロジェクトのリードを依頼しつつ、人材育成の場としても活かしたいと考え、メルセネールに相談
- 「人材育成と事業化実現の両立を意識した支援バランス」「新規事業に不慣れなメンバーでも安心して相談できるコミュニケーションスタイル」「Webと現地訪問を併用したメンタリング体制」を決め手に依頼
- プロジェクトの壁打ちに加え、事業検討に必要なフレームワークや思考法を体系的に学べる講義を実施。検討チームの理解促進と検討の土台づくりを支援
- 単なる助言にとどまらず、議論の促進や構造整理を通じてプロジェクト全体をリード。「講義⇆メンタリング⇆実践」のサイクルを回すことで、事業検討と人材育成の両立を実現し、全アイディアの採択にも貢献した
JR博多シティは、JR九州グループの駅ビルホールディングスに属し、不動産事業の中核を担う会社です。
これまでメルセネールは経営・事業の視点を生かし、新規事業創出に向けた仕組み作りと事業検討者の伴走に携わってきました。その実績が評価され、株式会社JR博多シティ様から同社が行う新規事業創出に向けた「収益力強化プロジェクト」の支援をご依頼いただきました。
今回は本プロジェクトの事務局メンバーである、株式会社JR博多シティ 企画部 担当部長の阿部様、山田様に依頼背景をはじめ、メルセネールがもたらした効果を伺います。
目次
求めていたのは「新規事業に不慣れなメンバー」に伴走できるメンター
JR博多シティ様が実施されている『収益力強化プロジェクト』について簡単に教えてください。
阿部:本プロジェクトは、社員のアイディアをもとに新たな収益源を創出する、実践型の取り組みです。第1回は2021年度に開催しました。この背景にあったのは、コロナ禍による商業施設の売上低下や先行きの不透明さです。そのため当初は新規事業の立ち上げというよりも、既存事業の領域拡大に軸足を置いた構想としてスタートしました。第2回となる今回は、業績の回復に伴って社内に前向きなムードが広がっていたこともあり、「今こそ新しいチャレンジを」との思いで実施しました。
プロジェクトでは、社員から募ったアイディアのうち、審査を通過したものをチームで具体化していきます。発案者自身もそのメンバーとして加わり、最終的には経営陣へのプレゼンを経て、事業化を目指します。
第2回となる2024年度の開催にあたり、外部の伴走者を検討されたのには、どのような背景がありましたか?
阿部:第1回では、管理職以下の社員を対象に約50名が参加し、複数のチームが立ち上がりました。事務局やチーム支援も含め、全て社内で対応していましたが、社員の多くが事業開発に不慣れだったこともあり、運営側にとっても非常に負荷の大きいプロジェクトとなりました。
こうした経験を踏まえ、第2回では運営負担を軽減しつつ、プロジェクトを人材育成の場としても活かしたいと考えるようになりました。ただ、知識やノウハウのない領域に社内だけで取り組むには限界もあるため、今回は外部の伴走者を迎える判断に至りました。
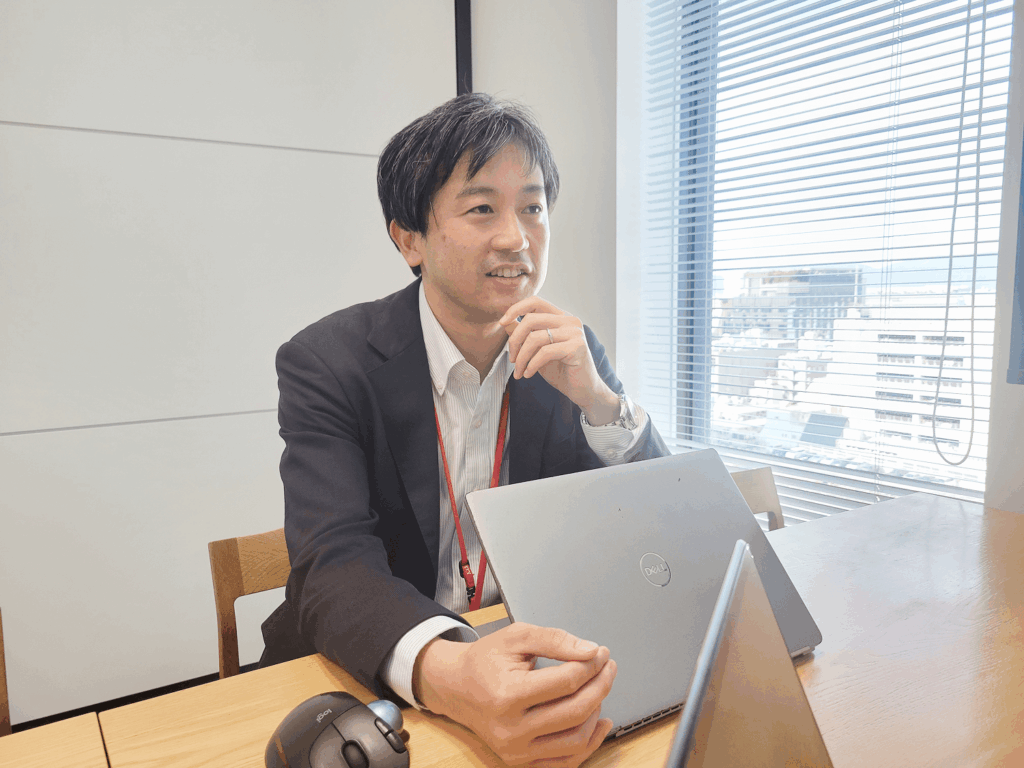
(阿部様)
今回、実際に30社弱から提案を受け、その中からメルセネールを選ばれたと伺いました。決め手は何でしたか?
阿部:選定にあたって、私たちが重視したポイントは大きく3つありました。1つ目は「人材育成と事業化実現のバランス」です。育成だけでなく、将来的な収益化も見据えて、事業を実行フェーズまでしっかり伴走できるかどうかを重視しました。その点で、アドバイスにとどまらず柔軟に動いてくれるメルセネールのスタイルは理想的でした。
2つ目は、「顧客視点を持った新規事業開発」です。どうしても自社アセットありきの発想に偏りがちでしたため、今回は顧客ニーズの検証プロセスそのものを社内に根づかせたいと考えていました。実際のインタビュー支援まで含めて対応できる点で、メルセネールなら任せられると感じました。
3つ目は、「コミュニケーションスタイル」です。新入社員も含めた多様なメンバーが参加するため、コンサルタントとの接点が少ないメンバーも多くいました。面談を重ねる中で、メルセネールなら目線を合わせ、丁寧に信頼関係を築いてくれそうだと感じられた点が大きかったです。
さらに、Webと現地訪問を併用したメンタリング体制も安心材料でした。福岡に拠点を持つ企業からも応募はありましたが、月2回の現地訪問を含む提案は、私たちの希望にも合致していました。
今回、メルセネールにはどのような点で期待をされていましたか?
阿部:参加メンバーの多くが新規事業そのものに不慣れなため、「講義と実践をどう組み合わせて進めてもらえるか」には特に期待していました。単なる座学ではなく、実務に活かせる内容をその場でフィードバックしてもらえるような支援が必要だと考えていたからです。
山田:私自身、第1回のプロジェクトに参加した際、「これで合っているのか分からない」と不安を抱えながら進める場面が多くありました。だからこそ、疑問が生じたとき、すぐに相談できる存在がいることが、プロジェクトを進めるうえでは重要だと感じていました。 他社での支援実績も伺う中、メルセネールなら、私たちの状況にも寄り添いながら伴走してくださるのではと期待しました。
講義×メンタリング×実践──人材育成と成果を両立した支援サイクル
今回、メルセネールが実施したご支援内容について、簡単に教えてください。
阿部:本プロジェクトは、「アイディア検討フェーズ」と「事業化検討フェーズ」の2段階構成となっており、メルセネールには後半の事業化検討フェーズをご支援いただきました。
今回、応募のあった複数のアイディアの中から、3案が事業化検討フェーズへ進みました。
事業化検討フェーズは2024年8月下旬から約3.5ヶ月にわたって実施され、新入社員から執行役員クラスまで、約20名が参加。期間中は、プロジェクトの壁打ちに加え、事業検討に必要なフレームワークや思考法を体系的に学べる講義形式の支援も行っていただきました。
単なるアドバイスに留まらず、議論の促進や構造の整理まで丁寧に伴走いただいたことで、プロジェクト全体の質が高まりました。新規事業に不慣れなメンバーが多い中、「講義⇆メンタリング⇆実践」のサイクルが機能したことで、人材育成の観点でも大きな手応えを感じています。
メルセネールが伴走したことで、どのような変化や成果があったと感じていますか?
阿部:最も大きな変化は、「顧客の声を聞く」という姿勢の定着です。当初、メルセネールから「お客様へのインタビューを取り入れるとよい」と提案を受けた際は、正直なところ社内で本当に実行できるのか不安がありました。というのも、当社にはお客様に直接ヒアリングするよりも、自分たちで仮説を立てて動く文化が根づいていたからです。
そうした背景も丁寧にくみ取りながら、各チームの状況やアイディアに応じた柔軟な伴走をしてくださったのが印象的でした。特に初期段階では、「顧客のリアルな声を、アンケートではなく対話から得る」ことの意義を繰り返し伝えていただき、徐々に社内の理解も深まっていきました。
実際には、すぐに動き出したチームもあれば、ためらっていたチームもありましたが、一度取り組み始めると議論の質が大きく変わり、アイディアの方向性を見直す動きにもつながりました。最終的なプレゼンの完成度も高く、インタビューによる成果は非常に大きかったと感じています。
山田:私も今回、あるチームの一員として参加しましたが、実際にユーザーの声を直接聞けたことは大きな学びになりました。最初は緊張もありましたが、回数を重ねるうちに自然な対話ができるようになり、アイディアが少しずつ形になっていく手応えを感じられました。
また、メンタリングの場で得た知見をすぐに実践へ落とし込めた点も印象的です。伴走があったことで検討の方向性に迷わず、安心して取り組みを進められました。前回と比べて、行動や思考の質にも前向きな変化が生まれたと感じています。

(山田様)
最終報告会には、全てのアイディアが合格
実際にプログラムへ参加された社員の皆様からは、どのような声が届いていますか?
山田:プロジェクト終了後のアンケートでは、プログラム内容や伴走型のメンタリングに対して、好意的な声が多く寄せられました。「これまで曖昧だった新規事業の進め方が整理できた」「自分たちでも動ける手応えを得られた」など、前向きなコメントが多かったです。
中でも印象的だったのは、「お客様の声を聞くこと」への意識の変化です。例えば、ある参加者は「自分たちはテナント様に場所を貸す側」という立場にとらわれていましたが、インタビューを通じて、「顧客の声を直接聞くことも自分たちの役割だ」と捉え直すことができたようです。
最終報告会には社長をはじめ、取締役の皆さんも参加されていましたが、実際に提案を聞いて、どんな反応がありましたか?
阿部:3案とも無事に通過し、議論も「やるべきかどうか」ではなく、「どうやって実現するか」という前向きな方向へ進みました。顧客インタビューを重ねた上での提案だったこともあり、内容に説得力があり、ニーズの強さがしっかり伝わったのだと感じています。
プレゼン自体も、要点を押さえて端的にまとめられており、メルセネールの支援による成果を強く感じました。特に印象的だったのは、報告会の冒頭でメルセネールが「このプロジェクトで大事にしてきた視点」を丁寧に説明してくださったことです。経営陣にも、プロの伴走のもとで進められてきたことが伝わり、プレゼン全体への信頼感にもつながったと思います。参加者にとっても、自信と達成感につながる、良い場になったはずです。
3案全てが「次のステップ」に向けて動き出す

今回採択されたアイディアは、現在どのような状況にありますか?
阿部:採択された3つのアイディアには、それぞれ正式な担当部署と担当者がアサインされ、現在もローンチに向けた検討が続いています。一部の事業案は、実際にお客様にテストしていただく段階に到達しており、現在はその結果を踏まえ、事業計画をブラッシュアップしているところです。
今後、どのように『収益力強化プロジェクト』を発展・継続させていきたいとお考えですか?
阿部:今回の取り組みは、新たな事業の創出だけでなく、人材育成の面でも大きな効果がありました。今後も定期的に継続していける形が理想だと考えています。
また、今回の経験を通じて、アイディアの創出からビジネスプランの具体化までを一貫して支援できる体制の必要性も強く感じました。プログラム全体の設計段階から伴走してもらえることで、よりスムーズかつ実りある進行ができると思います。
メルセネールのように、第三者としての客観性を持ちながらも、社内の思考や主体性を尊重し、適切なタイミングで気づきを与えてくれる存在は非常に貴重です。社内では見落としがちな論点に気づけたことも、大きな価値だったと感じています。
今回の支援を踏まえて、どのような企業にメルセネールをおすすめしたいと思われますか?
阿部: いわゆる、コンサル的なコミュニケーションに抵抗のある企業には、フィットすると思います。押しつけがましさがなく、それでいて本質的なコンサルティングを受けられる。その絶妙な距離感が、私たちには合っていました。
山田:新規事業にこれから取り組む企業や、これまでの進め方をアップデートしたいと考えている企業には、特におすすめしたいです。私自身、今回が初めてコンサルタントの方とご一緒する機会でしたが、メルセネールのような伴走者がいなければ、これまでの延長線上でなんとなく進めてしまっていたかもしれません。
講義を通じて知識をインプットしながら、自分たちのペースで考えを深めることができましたし、常にフラットな姿勢で問いかけや視点を提示してくださったのが、とても心強かったです。現場にとっても、安心して試行錯誤できる環境だったと思います。
最後に、これから新規事業プロジェクトに取り組もうとされている他社の方々へ、メッセージをお願いします。
阿部:新規事業には「これが正解」という道筋がない分、自分たちの意思や信念がなければ判断できない場面が数多くあります。だからこそ、伴走してくれるパートナーがどんな思想やスタンスを持っているかは、とても大切だと思います。 その点、メルセネールは事業への信念と、現場での実践知の両方を持ち合わせていて、私たちが目指す方向性と自然にフィットしていました。ブレずに進められたのは、その土台が共有できていたからこそだと感じています。
新規事業メンタリングサービスについて詳しく見る

